
水俣×福島交流ツアーを終えて/島貫真(エチカ福島)
8月8日~12日の水俣×福島交流プログラムを終えて、1万字近くにわたる訪問記を島貫さんは寄せてくださった。
その訪問記の最後の二章を抜粋して紹介したい(MINAMATA IMPACT編集部)
 水俣でたくさんの方のお話をきくうちに、この認定や審査、訴訟などのシステム自体が人びとの生活をどれだけ歪め圧迫してきたのか、を思い、胸が苦しくなってきた。
水俣でたくさんの方のお話をきくうちに、この認定や審査、訴訟などのシステム自体が人びとの生活をどれだけ歪め圧迫してきたのか、を思い、胸が苦しくなってきた。
事情はもちろん大きく異なる面もあるが、東電や国のさじ加減で、強制避難か自主避難かの区域も分かれ、行政の区分で補償の有無も線引きされて、結果として人びとの分断や差別、対立が深まるということも経験してきた。
福島では行政と企業の学習がさらに進み、明るい未来のために「復興」や「処理水」「風評加害」などのキーワードを振りまき、「科学的」に問題がないことをことさらに言いつのって「分断」を乗り越えて絆を、みたいなノリになっていく流れが加速中だ。
水俣の70年に比較すれば、まだ福島の「歴史」は1/5に過ぎない。
私たちがどのような歴史をつくっていくのか、は、例えばこういったエチカ福島の営みの中で得た出会いを、どう福島に持ち帰って生かしつつ「石」に刻んでいくかに係っているのだろう。
こうしてこの交流の感想を書くことが、その一歩になりえるのかどうか。
正直にいえば、私自身は「福島」を背負うような当事者の「資格」などない、と考えている。避難をしたわけでもないし、生業を奪われたわけでもなければ、東電事故関連死を身近な人が経験した、というわけでもない。 敢えて一番悔しかったことといえば、江名や小名浜、四倉などの港から水揚げされてきた海の幸を、いわきの誇りといて語れなくなったこと、だろうか。
そんなことは本当に小さなこと、かもしれない。震災直後の時期を除けばお魚はスーパーで手に入るし、最近では、魚種によっては「常磐もの」だって買えるようになった。生活の日常は、何事もなかったように「普通」になったようにも見える。
多くの市民が「普通」を手にして、起こったことを忘却してしまうという現実も進行しているようにすら思える。
でも。
それでも。
そんな形で、つまりは日常と忘却のセットと引き換えに「復興」を手にしていくことには、どうしても納得できない思いが残る。その理由が今回の水俣訪問でおぼろげながらわかってきた。
 「歴史における当事者とは誰のことか」
「歴史における当事者とは誰のことか」
と言ったら話は大げさすぎてしまう。当事者の声こそが重要であるならば、テープや活字で残せばよいとも言える。映像でアーカイブを作っても良い。そしてもちろん資料としてそれが重要であることは間違いない。けれど、今回水俣で直接お話を伺い、自分の足で現場にたち、水俣の食を味わいながら上記のような濃密な体験をしたことは、おそらくアーカイブを紐解くこととはすこし異なった次元の重要な意義を持つ。
独断は所詮いつ言っても独断だから、うっかり書いてしまえばつまりは、
「水俣の『記憶』を生身の人から生身の自分に手渡された」
と感じたのだった。伝える人がいなくなれば、やがて記憶は消える。それは決して資料という外部に残せばいいという種類のものではない。
私たちが身体を通して内側からそれを感じ、それをまた繋いで外側に伝えていくこと。
「公共的記憶」とは、個人的な体験や感想、共感のレベルで受け継がれるだけではなく(それはもちろん大切な核の一つなのだが)、共有される臨界面としてのこの自分の体を通して、どこか別のところにまた「いごきつづける」経験のことなのではないか、と感じたということだ。
もとよりそれを『チェルノブイリの祈り』とか『苦海浄土』とかのレベルまで昇華することは望むべくもない。が、私は今回の水俣の方々の「歓待」から、歴史としての記憶、記憶としての歴史、あるいは倫理としての記憶、倫理としての歴史(言葉をどんな組み合わせにしたらフィットするのかすらまだわからないが)というようなものを受け取ってしまったような気がしている。ある意味、えらいことになった。
 私は、今回この場所で受け取ったその『記憶』を内面化したのではない。あたかも頂戴した薄絹を「肩にかづく」ことになったのではないか。そして、折に触れてはその「水俣」から受け取ったあえかなしかし決して身から切り離すことのできない羽衣のような薄絹を、身にまとっていると気付きつつ生きていくことになったのではないか。
私は、今回この場所で受け取ったその『記憶』を内面化したのではない。あたかも頂戴した薄絹を「肩にかづく」ことになったのではないか。そして、折に触れてはその「水俣」から受け取ったあえかなしかし決して身から切り離すことのできない羽衣のような薄絹を、身にまとっていると気付きつつ生きていくことになったのではないか。
おそらく傷は一義的には当事者のものだ。それはその人とともにそこにある。そして私は傷を共有することはできない。おそらくそれは共感も理解も受け付けない面を持つ。そうであればこそ、語りを聴いてヴォイスレコーダーに記録するだけではたりない。また自分で語り継ぐといっても、幾分かは劣化コピーになり、あるいは物語られた定型に切り詰められていくだろう。だから威勢のよい話し方は止めておいたほうがいい、と思わず自戒する。
けれど、一旦身にまとった『記憶』を忘れずに生きていくことは不可能ではない。そしてそれは、基本的には語れない。それを自分で見ることもかなわない。敢えて言うなら、あたかも衣擦れのような「音」を私に聞こえさせてくれるとでもいった方がよいだろうか。
それでも「記憶」を受け止め、それを身にまといつつ、自分の身体はそこからどんなことを改めて表現できるのかできないのか、を問うことはできる。生きているかぎり、『記憶』を身にまとっていくことは可能だし、もしかするとそれを今回の体験は私にそういうことを「強いてしまった」のかもしれないとすら考えたりもするのだった。
- まとめに代えて●
さて最後の話になる。
今回出会った水俣のみなさんは、一人の例外もなく、強い。
それが、トーナメント理論的に強い人だけが語り続けることができたということなのか、それとも水俣という場所が持つ共同体というか社会というか文化伝統の蓄積というか磁場の力なのか、あるいは水俣病事件という苦難が(私に)「強さ」と感じられているだけで、それはそんな風に「強さ」などと丸められてはならないものなのか。
分からない。
しかしなぜかはわからないまま、その「力」の存在を感じている。
しかもそれは、身体の中から人の心と体と頭を「いごかす」力だ。愛の反対が無関心だとするなら、トライや宇城市の事例の対極にいる(いさせられている?)水俣で出会った人たちは、敢えていえば愛の力を内側から放っている。

この「愛」を、上述の「記憶」と響き合わせて考えることはできないだろうか。つまり、受け取ったものを手渡していく『記憶』の強度とでもいうものが、みなさんの中から感じられるということなのだが。 また、身体の中から感じる力のイメージと、水俣で味わった食べ物の美味しさとは、どれほどの関係があるのだろうか。それはもう一度水俣を訪問したとき、美味しいもの一緒に食べながら、もう一度今度は聞いているばかりではなく、語り合えたら、と思う。
今年は注文しなかったけれど、来年は水俣の甘夏をまた取り寄せよう。お茶が切れたらまた追加しよう。
とりとめなく印象深かったことを、そしておそらく幾分かは誤解しながら受け取ったものを単純な印象や感想で繋いだだけの文章になってしまったが、これが正直な現状報告なのだから仕方がない。
水俣と出会ったいわき(福島)の住民の一人としては、これからこの出会って受け取ったことどもと、長く長く付き合いを続けていくことになる。それだけは間違いない。
そのとき、身にまとった薄絹のようなこの「記憶」が、「自分だけ孤立している」という「錯覚の弱さ」を補ってくれる羽衣(マッチョなモビルスーツのようなものではなくて)になってくれればいい……と思うのは他力本願にすぎるだろうか。
Writer Makoto shimanuki (researcher in philosophy)
ライター/エチカ福島 島貫真(元福島県立高校教員・国語科)
(この記事の元となった水俣訪問ツアーは、科学研究費補助金基盤B「分断された地域コミュニティの「対立・葛藤変容」に向けた分析とプログラムの提示」(研究代表者・石原明子、研究課題番号23K20062)の「水俣×福島交流プログラム」の一環で実施したものです。)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
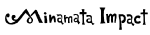
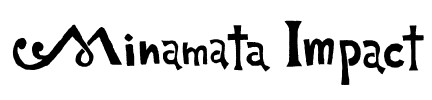









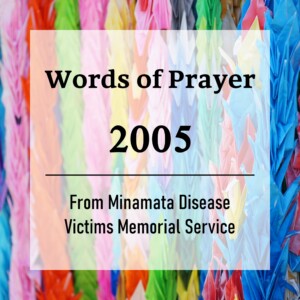




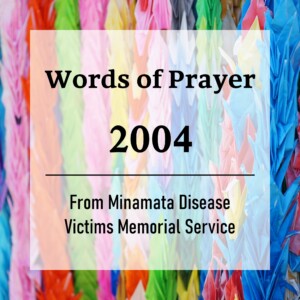

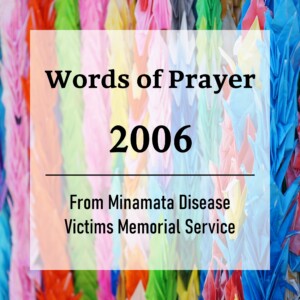
この記事へのコメントはありません。